
人は時として、ちょっとしたきっかけで新しいものを見る眼を持つことがある。
1976年、宮津市の上世屋にあった日置中学校上世屋分校が休校になる時、黒坂正文に届けられた一通の手紙をきっかけに始めた小さなコンサート「おいで一緒にin上世屋」
そのコンサートがなんと10年間続いた。それを続けてきたものは何だったろうか?
かつての感想に「よかった、私たちの生活に無いものがここにあった。また来年新しい仲間を連れてきます」というのがあった。当時の私たちの生活には無いものがここにはあった。そのことがコンサートを続けてきた理由かもしれない。
当時はブラザ合意からバブル景気が始まる前であり「経済至上主義」ともいうべき社会状況の中で、「中央」がもてはやされ、マスコミたれながし文化が大氾濫。「自分たちの歌」という実感のないものばかりだった。
それに加えて、多くの子どもたちが自ら命を絶つという事実があり、世の中は人と人とのつながりがばばらばらにされていくような動きを感じていた。
「しっかりと足を地に着けて踏ん張り、将来への展望を見つけ出したい。」そんな思いがコンサートを通じてはじけた。
そして呼びかけた。「おいで一緒に!」 |
なぜ「in上世屋」から「in世屋」へ?
第10回コンサートから25年が過ぎ、学舎の灯火一つをとっても、駒倉、木子についで上世屋の灯火が消えた。
そして下世屋の灯火も消え、旧世屋村から学舎がなくなり、さらに日置の灯火も揺らごうとしている。
丹後半島の脊梁をなす山々(鼓ヶ岳、高岳、岳山)の山麓に点在してきた村々。
湧水を生かし棚田を開き、自然を恵みに変える知恵と技術を継承し、慎ましい暮らしを営んできた村々。
これらの村の滅びと衰亡は、農の滅び、自然の滅び、そして子どもらの発達の滅びの予言であったことを今痛切に思う。
けれども、苛酷な状況に揺られながら世屋の里々はしぶとく、しなやかに、地域に当たり前に暮らせる幸せにこだわった。
そして知恵を出し合い続けた里でもあった。
若狭の海のはるか向こうに加賀の山を望み海と空をつなぐ村々。

住民同士のつながりを大切にしあう村づくり。
肩を寄せ合う家々の温かさ、空に開けた村の伸びやかさ。
名もない神々の宿る自然に刻まれた時間。里山に育まれる命の多様さ。寺社の由緒の味わい深さ。
それらは、世屋の里が未来へ放つ光芒のように思われる。
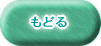
|
